
vol.3「夢の砦」
新横浜にラポールという施設があるのをご存知だろうか。正式には「障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール」。場所をいうとサッカーの日産スタジアムの隣りだ。稼動してちょうど20周年になる。僕にこの施設の存在を教えてくれたのは、冬季パラリンピックで日本人初の金メダリスト(98年長野、チェアスキー滑降)になった大日方邦子さんだった。最初、雑誌の対談でお会いして、後にラジオ番組にゲスト出演してもらった。神奈川出身の大日方さんはラポールを「私のホーム」と言った。
僕は障害者スポーツという呼び方があまり好きじゃない。ただスポーツだけがあると思っている。それは選手らに会って取材をする度、何度も思ったことだ。世間の人はあまり選手らの素顔を知らないから「障害者」と「アスリート」の両立をイメージしにくいらしい。「障害者」というと、とにかくもう同情してやさしく接すべき、保護すべき存在だと思っていたりする(僕はパラリンピック・アスリートの取材をしてると言っただけで、「やさしいんですね」と言われたことがある)。
実際の彼ら彼女らはハンパないエネルギーの持ち主だ。少なくともアスリート・レベルの選手は体力もガッツもとんでもない。まぁ、それでも間違いなく「障害者」ではあるから、理解や配慮は必要なんだと思う。だけど、こっちが夏バテでぐったりしてるとき、ガンガンに走り込んでるパラリンピック・アスリートを取材すると、生き物として「強者」は向こうで「弱者」はこっちじゃないかなぁという気になる。

加藤有希さん(右)とご主人の貴行さん(左)
ラポールの職員にロンドンパラリンピックに出場する選手を紹介していただいた。陸上短距離(脳性マヒ)の選手だ。既にアテネ、北京に出場していて、アテネでは100メートル走(クラスT−36)で銅メダルを獲得されている。「ロンドンは三大会連続ですか、すごいですね」と申し上げると、実は四大会連続のはずだったそうだ。アテネの前に「幻のシドニー」があった。この話がすごく面白い。
読者はパラリンピックアスリートが何故、パラリンピックアスリートになるのか、その発端のところを想像してみたことがあるだろうか。物語のそもそものスタート。起承転結でいえば「起」。加藤有希さんの場合、(きびしい家庭で負けずぎらいに育ったとか、そもそも走るのに自信があったというのもあるけれど)、物語が始まりは「幻のシドニー」じゃないだろうか。
シドニーの開催前年、有希さんはたまたま「東京都障害者スポーツ大会」に出場する。これは文字通りたまたまだ。軽い気持ちだった。走るのは気持ちいい。脳性マヒは緊張すると身体がこわばってしまったり、手先が思うようにならなかったり、ふたつのことが同時に考えられなかったり、色んな不自由があるんだけど、風のように走るのは気持ちいい。有希さんは「目立ちたかった」。僕はその発端のところにあった感情にしびれるなぁ。目立ちたい。古今東西、あらゆるアスリートの最初のモチベーションだ。
で、その大会で彼女は100メートル走で優勝してしまう。それも日本記録を2秒近くも縮める驚異的な走りだった。大変なことになった。関係者が騒然とする。無名の新人がシドニーパラリンピックの代表候補に躍り出る。だけど、後に行われた最終選考会で有希さんは標準記録がマークできなかった。極度に緊張して身体が硬直してしまったのだ。
有希さんは自腹でシドニーパラリンピックを見に行くことにした。ご主人の貴行さんといっしょにスタンドから競技を見る。涙がこぼれてきた。悔しくてたまらない。「あそこに自分がいるはずだったのに」。それが物語の始まり。

貴行さんのアドバイスに耳を傾ける有希さん
そして起承転結の「承」には新横浜ラポールが大いに役立ってくれた。地下の陸上トラックに毎日通う。加藤有希さんにとってもラポールは「ホーム」だ。彼女の本気を受けとめてくれる、かけがえのない場所だ。アテネではメダル獲得の感激に胸がふるえた。北京ではレース直前、関係者に激励されたことがプレッシャーになり、身体が緊張状態になってしまった。脳性マヒはパラリンピック関係者にも理解されてないんだなと落ち込む。たぶん関係者は何も考えず「がんばれ!」と声をかけたのだ。

もちろんロンドンパラリンピック前にこの原稿を書いているから、僕は物語の行方を知らない。まぁ、勝つと素晴しいなぁと思うけれど、勝ち負けより彼女自身、納得のいくレースができるのを願っている。ただ確実に言えることがひとつあって、有希さんが戻ってくるのをラポールのトラックコースはいつでも待ってるということだ。その栄光もその失意も、同じようにどっしり受けとめてくれるはずだ。
ラポールを訪れるのは有希さんのようなアスリートレベルの利用者だけではない。リハビリという段階の人もいる。親御さんに連れられて初めてスポーツするという子も来る。障害の程度も、年齢も性格もまちまちなのだ。それでも「夢の砦」を訪れるとき、人は積極的になっているはずだと思う。スポーツは仲間をつくるし、努力や達成感をもたらす。人を前向きにしてくれる。つまり、ラポールの施設全体、いたるところで沢山の物語が始まっているのだ。プールにも体育館にも、テニスコート、STT(サウンド・テーブルテニス室)にも人があふれている。
この小さなコラムを結ぶにあたって、もう一度「パラリンピックアスリートは何故、パラリンピックアスリートになるのか?」という問いに立ち返ることにしよう。ご紹介したいのは「障害者スポーツ」発祥についての物語だ。
1948年、ロンドンオリンピック開会式の日、イギリス南部にあるストーク・マンデビル病院の庭で、車椅子の入院患者によるアーチェリー競技会が行われた。それがパラリンピックの始まりだ。今年はオリンピックも再びロンドンへ戻ったわけだけど、パラリンピックも発祥の地へ戻ることになる。僕の考えでは、そのロンドンの病院も「夢の砦」のクチだ。自分たちには価値がある、自分たちの努力には価値があると信じた人が、発端のところをつくった。こう、ジーンとくると思いませんか?

コラムニスト
1959年8月13日生まれ中央大学在学中にコラムニストとしての活動を開始。以来、多くの著書を発表。ラジオ・テレビでも活躍。
Book
「サッカー茶柱観測所」「F党宣言!俺たちの北海道日本ハムファイターズ」ほか
Magazine/Newspaper
「がんばれファイターズ」(北海道新聞)/「新潟レッツゴー!」(新潟日報)ほか
Radio/TV
「くにまるジャパン」(文化放送)/「土曜ワイドラジオTOKYO」(TBSラジオ)ほか
Web
アルビレックス新潟オフィシャルホームページ
「アルビレックス散歩道」
Web
ベースボールチャンネル
「えのきどいちろうのファイターズチャンネル」
※タイトル・本文に記載の人名・団体名は、掲載当時のものであり、閲覧時と異なる場合があります。
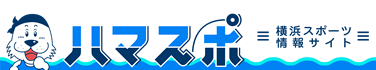 ハマスポ
ハマスポ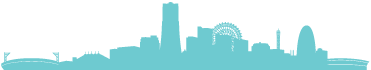
 お知らせ&トピックス
お知らせ&トピックス ページトップへ戻る
ページトップへ戻る ページトップへ戻る
ページトップへ戻る

